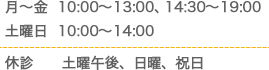風疹対策:妊娠前に知っておきたい抗体検査とワクチン接種
はじめに 「赤ちゃんを望んで妊活を始めたい」と考える女性にとって、見落とされがちな大切な準備のひとつが風疹対策です。風疹は発疹や発熱といった軽い症状で済むこともありますが、妊娠初期に感染すると胎児に深刻な影響を及ぼす可能性があります。 厚生労働省によると、2012〜2013年の流行では1万7,000人以上が風疹にかかり、その結果45人の先天性風疹症候群(CRS)の赤ちゃんが出生しました。この数字は、風疹が「妊娠世代にとって身近で現実的なリスク」であることを物語っています。 風疹の流行状況 風疹は周期的に流行を繰り返してきました。2018〜2019年にも全国で約5,000人の患者が報告され、特に首都圏を中心に流行しました。感染者の中心は30〜50代男性で、これは過去に十分な予防接種を受けられなかった世代に該当します。 国はこの世代の男性を対象に無料クーポンを配布し、抗体検査とMRワクチン(麻しん・風しん混合ワクチン)接種を推奨しています。 妊娠への影響 妊娠初期に母親が風疹に感染すると、胎児に先天性異常が起こる可能性があります。特に妊娠20週までの
子宮筋腫:症状チェックと最新の薬物治療・手術法
はじめに 「生理の出血が増えた」「お腹が張る感じがある」「貧血で疲れやすい」——こうした症状が続いている場合、その背景に子宮筋腫が隠れていることがあります。子宮筋腫は女性に非常に多い良性腫瘍で、30代以上の女性の約20〜30%が経験するといわれています。 症状が軽く無症状のまま経過することも少なくありませんが、重症化すると日常生活に大きな影響を及ぼし、不妊や流産の原因になることもあります。正しい知識と早めの対処が、健康と妊娠の可能性を守るために重要です。 子宮筋腫の基礎知識 子宮筋腫は子宮の平滑筋から発生する良性腫瘍で、悪性化することはごくまれです。閉経とともにエストロゲン分泌が減少すると自然に縮小する傾向があります。発症年齢は30〜40代が最も多く、妊娠経験の少ない女性や肥満、エストロゲンの分泌が多い体質がリスク因子とされています。また、母親や姉妹に子宮筋腫がある女性は発症しやすいことが知られており、遺伝的な要素も一部関与しています。 筋腫の分類(発生部位による) ・漿膜下筋腫:子宮の外側に発育する ・筋層内筋腫:子宮の壁の中にできる最も一般的
ホルモン補充療法(HRT):更年期女性に本当に必要?リスクと効果
はじめに 40代後半から50代にかけて、多くの女性が経験するのが更年期症状です。ホットフラッシュ(ほてり・発汗)、不眠、気分の落ち込み、関節痛など、症状は人によって異なり、その強さもさまざまです。厚生労働省の調査によれば、日本人女性の約50〜60%が更年期に何らかの不調を自覚しているとされています。 その治療の中心にあるのがホルモン補充療法(HRT: Hormone Replacement Therapy)です。欧米では一般的に行われていますが、日本では「乳がんや血栓のリスクが怖い」と不安を抱く方も少なくありません。本記事では、HRTの基本原理、効果と副作用、適応となる女性や注意点について、最新のデータを踏まえて解説します。 更年期に起こる体の変化 女性は閉経前後に卵巣機能が急激に低下し、エストロゲンの分泌が減少します。日本人女性の閉経の平均年齢は50.5歳で、閉経期を中心とする45〜55歳にさまざまな症状が出やすくなります。エストロゲンが不足すると、自律神経の乱れによりホットフラッシュや不眠が起こりやすくなり、骨や血管、脂質代謝にも影響します。
不妊と体重:痩せすぎ・太りすぎが妊娠に与える影響
はじめに 「妊活をしているけれど、なかなか妊娠しない…」そんなとき、多くの方が思い浮かべるのは年齢やホルモンバランスの問題かもしれません。しかし、意外と見落とされがちなのが「体重(BMI)」と妊娠の関係です。 厚生労働省の国民健康・栄養調査によると、日本の女性の約10%がBMI18.5未満の「痩せ」に分類され、一方で20〜40代女性の約20%が「肥満(BMI25以上)」とされています。つまり、日本では痩せすぎと太りすぎの両方が存在し、それぞれが不妊の要因となる可能性があるのです。 BMIと妊娠のしやすさ BMI(Body Mass Index)は「体重(kg)÷身長(m)の2乗」で算出されます。18.5〜24.9を「普通体重」とし、18.5未満は低体重(痩せ)、25以上は肥満と定義されます。 日本産科婦人科学会の資料では、BMIが18未満や25以上の女性は排卵障害による不妊のリスクが高いとされています。海外の大規模研究では、肥満女性は正常体重の女性に比べて妊娠までにかかる時間が約1.5倍長くなると報告されています。また、痩せすぎの女性も排卵障害の
生理の遅れ:ストレス?妊娠?病気?チェックすることが大切です
はじめに 「今月、生理が遅れている…」と気づいたとき、多くの女性がまず考えるのは妊娠の可能性でしょう。しかし、生理の遅れは必ずしも妊娠によるものではなく、生活習慣やストレス、さらには病気が関係していることもあります。厚生労働省の調査によると、女性の約3割が月経周期に不調を経験していると答えており、生理の遅れ自体は決して珍しいことではありません。 とはいえ、その背景には妊娠や疾患が隠れている場合もあり、放置せず正しい知識を持つことが大切です。 月経周期と「遅れ」の基本 医学的に正常とされる月経周期は25〜38日です(日本産科婦人科学会)。この範囲に収まらない場合、24日以内であれば「頻発月経」、39日以上であれば「稀発月経」とされ、3か月以上生理が来ない場合は「無月経」と診断されます。 日本人女性の思春期には約20〜30%が月経不順を経験するとされ、また更年期でも卵巣機能の低下に伴い不規則になりやすいことが知られています。 妊娠の可能性 避妊をしていない性交渉があった場合、生理の遅れが見られたときはまず妊娠を考える必要があります。妊娠検査薬は生理予